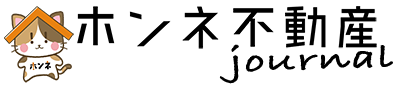賃貸物件を探す際、初期費用の高さに驚かれる方も多いのではないでしょうか。敷金、礼金、仲介手数料など、多くの費用がかかるため、資金計画は慎重に行う必要があります。本記事では、賃貸の初期費用を安く抑えるための具体的な方法を9つ紹介し、相場や交渉のポイントについて不動産のプロが徹底解説します。これから物件を探す方は、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸の初期費用の相場はいくら?
賃貸物件を借りる際の初期費用は、物件の家賃や条件によって異なりますが、一般的には家賃の4〜6か月分が必要と言われています。これには、以下の費用が含まれることが多いです。月額家賃が10万円の物件では、初期費用が40万~60万円ほどかかることになります。
| 入居月の家賃 | 日割り計算〜1ヶ月分 |
| 敷金 | 1ヶ月分 |
| 礼金 | 1ヶ月分 |
| 保証会社 | 0.5~1ヶ月分 |
| 鍵交換代やその他 | 各1万円〜2万円 |
| 仲介手数料 | 0.5~1ヶ月分+税 |
| 合計 | 家賃5ヶ月分前後が相場 |
この他にも、火災保険料や24時間サポートなどの費用が発生することがあり、物件や不動産会社(仲介会社・管理会社)によって異なるため、確認が必要です。
特に、都市部では物件の競争率が高く、初期費用が上がる傾向にあるため、地域や物件によっても大きく異なります。これに加えて、引っ越し費用や家具・家電の購入など、さらなる支出が伴います。そのため、初期費用の節約は多くの人にとって重要な課題です。次にご紹介する方法で、初期費用を効果的に削減していきましょう。

【必見】初期費用を安く抑える方法9選

ここでは、初期費用を節約するための9つの具体的な方法を解説していきます。不動産業界に精通したプロの視点から、賃貸のコストを抑える実践的なアイデアを見ていきましょう。
不動産業界の閑散期を狙う
賃貸物件の契約時期によって初期費用が異なることはご存じでしょうか。特に、不動産業界の閑散期(一般的に6月から8月)は、交渉がしやすくなり、初期費用を抑えるチャンスです。6月以降は引っ越し需要が減少し、空室が増えるため、オーナーや不動産会社が早く物件を埋めたいと考えることが多いのです。
この時期に物件を探すと、家賃や礼金、仲介手数料の交渉に応じてもらえる可能性が高くなります。具体的には、敷金や礼金を減額してもらったり、無料にしてもらえることがあるため、積極的に交渉してみましょう。
月初に入居して日割家賃を減らす
初期費用を抑える一つの方法として、「月初に入居する」という選択肢があります。賃貸契約を月の途中で開始すると、日割り家賃を支払う必要がありますが、月初に入居すれば、日割り家賃は発生しません。これにより、初期費用の負担を軽減できます。
例えば、月末に契約し、翌月の1日から入居する場合、日割り家賃が不要になるため、契約時に支払う金額が少なくなります。11~15日の入居(起算)だと翌月分の家賃も請求される場合が多いので、極力は中旬から下旬にかけての入居は避けたほうが初期費用は抑えれます。
【例:前家賃が不要の場合】
1~10日前後の家賃発生の場合ですと業者によって月内だけの家賃だけで入居できます。
家賃が仮に10万、1月14日契約起算日であれば18日分だけの家賃で良いので
家賃100,000÷31日=1日分3,225円
1日分3,225円×18日分=58,050円 となります。

このように、賃貸契約の開始日を月初に設定することで、日割り家賃の支払いを避けることができ、初期費用を賢く節約することが可能です。契約を結ぶ際には、タイミングを考慮することが大切です。
ただし、月末には翌月分の家賃が必要(毎月27日前後に翌月家賃1ヶ月分を支払うのが一般的)ですので、給料日が月末というかたは注意です。この方法はあくまで入居タイミングを調整することで、前家賃だけの支払いに抑え、短期的な出費を減らすことができるというだけで、支払う費用の合計を安くするといったお話しではません。遅かれ早かれ支払う費用ではありますので、あくまで初期費用がギリギリで足りない可能性がある場合の一時的な処置といったニュアンスで理解してもらえればと思います。
管理会社によっては1日入居でもその月と翌月分も請求してくる場合があります。左記は割合的にはそんなに多くはありませんが、せっかく入居日を調整したのに家賃2ヶ月を請求されるという事態にならない為にも、入居申込を入れる前に先に初期費用を確認しておくことをおすすめします。※もし不安な人は物件選びの段階で依頼している不動産屋の担当者に相談しておくと安心です
礼金なしの物件を探す
礼金は、日本独自の文化で、家主に対して感謝の意味を込めて支払うお金です。しかし、最近では「礼金なし」の物件も増えています。特に、築年数が経過した物件や、駅から遠い物件では、礼金なしで入居できるケースが多くなっています。礼金不要の物件を選ぶことで、1〜2か月分の家賃を節約できます。
礼金は返金されないため、できる限り避けたい費用の一つです。物件検索時に「礼金なし」や「礼金ゼロ」といった条件で探すことで、初期費用を大幅に抑えることができます。交渉次第では、礼金がかかる物件でも減額してもらえることがありますので、ぜひ試してみてください。
フリーレント物件を探す

フリーレントとは、一定期間の家賃が無料になる契約のことで「フリー=0円、レント=借りる」という意味です。フリーレント付き物件を選択すると多くの場合、1ヶ月から2ヶ月分の家賃が無料になるため、初期費用を抑えるだけでなく、引っ越し後の家計にも余裕を持たせることができます。
特に、オーナーが空室を埋めたいと焦っている物件や、似たような競合物件が多いエリアでは、フリーレントを条件に追加しているケースが多いです。物件検索サイトなどで検索条件に「フリーレント」を加えて検索すると、そういったお得な契約ができる物件がでてきます。
こういったフリーレントがついてる物件の場合、初期費用が安くなるのでオーナー側が赤字にならないように「1年未満で解約した場合に1ヶ月分の違約金」といった感じで、短期違約金が特約でついている場合が多いです。長期で契約する予定の人はあまり気にしなくて問題ありませんが、短期間で住み替え検討している人は注意。
火災保険を交渉して安いプランの保険に加入する
賃貸契約時には、火災保険に加入するのが一般的ですが、保険の内容によっては料金が異なります。必要以上の高額プランを選ぶ必要はないので、不動産会社や保険会社に相談し、安価なプランを探してみましょう。
また、不動産屋が指定する火災保険は2年契約で大体2万円前後が相場です。ですが、自分でネット申込の保険や共済などに加入すれば、多少の手間はありますが1年4000円前後で保証内容は同等レベルの保険に加入する事ができるのでおすすめです。
交渉の方法下記を参考にしてみてください。
- 身内や友達、知り合いの保険会社に加入したいと主張をする:身内や友達、知り合いにプロがいるとすれば業者もなかなか自社の保険を進めることに躊躇しますので、このことを伝えるだけで自分の選んだ保険に加入することができます。
- 指定された保険会社に必須なのか聞いてみる:管理会社から指定された火災保険会社に直接連絡して聞いてみてください。「代理店の管理会社より必ず御社の保険商品に入ってと言われました、本当にそうなのでしょうか?」そうではないとの答えが得られれば交渉が進みます。
- 大手不動産管理会社の物件を選ぶ:大手不動産管理会社では、自分が選んだ保険に入りたいと言えば了承してくれるケースが多いです。
また、交渉相談が通る可能性を上げる方法として、
- 保証内容がしっかりした保険(借家人賠償1000万円以上)に加入
- 加入手続き後に証明書を提出する(どの保険に加入したかの証明)
- 加入中に勝手に解約しない事を約束(返金目的で途中解約するのは絶対NG)
- 賃貸契約の更新時に自分で契約更新の手続きを行う事を伝える
上記をセットで伝えて約束すれば、交渉通る可能性をグッと上げることができます。
【おすすめの保険会社】
都民共済→1年間で約2,500円 (東京都内の物件に限る)
http://www.tomin-kyosai.or.jp/product/fire/guidance.html
日新火災→1年間で約4,000円 (全国)
http://direct.nisshinfire.co.jp/oheya/
チューリッヒ→1年間で約3,610円 (全国)
https://www.zurich.co.jp/ssi_kazai
オプション費用は交渉して外してもらう

賃貸契約には、室内消毒・除菌費、虫駆駆除費、24時間サポート、新生活応援パック、消化器代、書類作成費など、様々なオプション費用が含まれることがあります。これらのオプション費用は、入居者側(契約者)にとって必要ではないことが多いため、不要と感じる場合は交渉して外してもらった方が良いです。
例えば、新築未入居の物件であれば室内抗菌や鍵交換代は不要ですし、虫駆除費用なども自分でバルサンを炊いて対策をするのであれば、不要だったりします。そのため、オプションの内容を確認し、必要なものだけに絞り、不要な費用は外してもらうように相談しましょう。
書類作成代/契約事務手数料を交渉で外してもらう
前述したオプション費用のお話と同じく、「契約事務手数料」や「書類作成費」を契約時に請求される場合があります。この費用については、不動産会社によって異なります。これらの費用も交渉次第で削減や免除が可能なことがあるので、契約前に確認し、交渉することをおすすめします。
相場は5,500円〜11,000円 高いところで22,000円ほど請求される場合があります。本来はこういった費用は仲介手数料の中に含むべき費用であり、仲介手数料1か月分+税と別にこの項目で費用を請求するというのは宅建業法違反となります。そのため、書類作成費・契約事務手数料などの名目で費用を請求された場合は、交渉相談をするか、複数社に見積もり依頼を行い、安くなる会社がないか調べてみましょう。
もし、見積もりした他社で安くなる場合は、その会社に依頼すれば安くなります。逆に、各社の費用が同じだった場合は、管理会社(オーナー)が費用を請求している事になるため、依頼する不動産屋を変えても費用は変わりません。この場合は不動産屋を通して管理会社(オーナー)に交渉をして削減してもらう必要があります。
管理会社(オーナー)がオプション料金や書類作成費/事務手数料などを特約で入居条件として請求している場合は、交渉しても聞いてもらえない場合があります。この場合、契約自由の原則という考え方が優先されるため、強気で交渉したとしても入居審査で断られる場合が多いので、交渉を粘るというよりかは、最初からそういった費用を請求しない管理会社(オーナー)の物件を選ぶ事をおすすめします
上場企業の法人契約名義で借りる
大企業に勤めている方は、法人契約名義で賃貸物件を契約することができる場合があります。法人契約では、企業が契約者であり保証人になるため、保証会社の利用が不要になるため、その分の保証料が安くなる(0円になる)ことがあります。
また、企業が家賃補助を出すケースも多いため、初期費用だけでなく月々の支払いも抑えられる可能性があります。自分の勤務先がこうした制度を持っているか確認し、利用できる場合は積極的に活用しましょう。
仲介手数料を交渉して安くしてもらう

仲介手数料の相場金額は、家賃の1ヶ月分+税です。理由としては、法律で最大1ヶ月分+税までと定められているためです。これはあくまで上限であり、交渉次第では半額や無料にできる場合があるので契約前に不動産業者に確認し、交渉する価値があります。
仲介手数料については以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご覧ください!
>>仲介手数料が安い不動産屋ランキング9選!無料~半額のおすすめ不動産会社
>>賃貸物件の仲介手数料で家賃1ヵ月分が違法?0.5ヶ月が原則?安くする方法とは
>>賃貸物件の仲介手数料の交渉タイミングとは?値切るコツ&交渉の仕方を伝授
交渉せずに仲介手数料無料にする方法

前述したように、不動産屋によっては、手数料を割引してくれる場合があります。できる理由としては、裏話になりますが、仲介手数料の他に貸主や管理会社より仲介を行う不動産屋に対して手数料が出る場合があります。手数料は別名がAD/広告料/業務(報酬)委託料と呼ばれています。そのような物件の場合は、借主側の仲介手数料を割り引いてくれる不動産屋もあるため、交渉に応じてくれる不動産屋を選ぶことも初期費用削減の鍵となります。

そのため、こういった手数料の話をオープンに話してくれる不動産屋に依頼をすれば、仲介手数料を無料または割引にしてくれる場合が多いおでこうした不動産屋を探し、物件を見つけると交渉などしなくても仲介手数料を安く契約することができるためオススメです。
初期費用が払えない場合の対処法
初期費用を払えない場合の対処法として、いくつかの選択肢があります。これらの方法を検討して、無理のない賃貸契約を進めてください。
クレジットカードで分割支払いにする
不動産会社によっては、クレジットカードでの初期費用支払いに対応しているところがあります。クレジットカードで支払えば、分割払いやリボ払いに変更することができるため、一度に多額の費用を支払う必要がありません。
ただし、クレジットカードの利用には金利や手数料が発生する場合があるため、慎重に検討しましょう。クレジットカードのポイントを貯めるメリットもあるため、自分に合った支払い方法を選ぶことが大切です。
不動産屋に相談をして初期費用が安い物件を選ぶ
不動産会社に初期費用を抑えたいことを直接相談し、予算に合った物件を紹介してもらうのも一つの手です。物件によっては、初期費用が抑えられるキャンペーンを行っていることもありますので、気軽に相談してみましょう。不動産業者は、予算に合わせた物件を提案してくれることが多く、交渉を進める上で有利に働くことがあります。
また、礼金なしやフリーレントの物件を優先的に探してもらうことで、初期費用を大幅に抑えることができる場合もあります。自分だけで物件を探すのが難しい場合、プロの力を借りて効率よく進めましょう。
初期費用が安い不動産屋を選ぶコツ
不動産屋によっては、初期費用が大きく異なります。初期費用を考えるために、適切な業者を選ぶコツも重要です。
仲介手数料無料の業者に相談
初期費用を大幅に抑える方法の一つは、
仲介手数料無料を売りにしている業者に相談することです。これにより、家賃1ヶ月相当の費用がかからないため、初期費用を大幅に削減できます。
ホンネ不動産なら仲介手数料0円にできる
東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪市内エリアを対応している「ホンネ不動産」であれば、貸主(大家さん)からの仲介報酬(手数料)を最初から開示しているので、面倒な駆け引きや交渉をすることなく貸主から手数料もらえる物件の場合、仲介手数料0円で契約することができます。
よく仲介手数料0円から契約できると謳っておきながら、別の項目(除菌消臭・虫駆除サービス・24時間サポート・消火剤など)を上乗せ請求をする不動産屋がいますが、ホンネ不動産ではこういった不要なオプション料金なども請求されませんので、初期費用最安クラスで適正な価格で契約をする事ができます。
賃貸の初期費用を安くする方法まとめ
賃貸の初期費用を抑えるためには、契約時期や物件の選び方、オプション費用の交渉が重要なポイントとなります。特に、閑散期を狙って契約することや、礼金なし・フリーレントの物件を探すことで、初期費用を大幅に削減できる可能性があります。また、交渉によってオプション費用や仲介手数料を減らすことも有効です。払いが厳しい場合はクレジットカード分割払いを活用し、資金負担を減らす方法を検討するとよいでしょう。
しっかりと準備をして、コストを抑えた賃貸契約を目指しましょう。
【初期費用に関しての関連記事】
各種初期費用やその節約方法などについて詳しく解説しています。費用削減にぜひお役立てください!
これから引越す予定の人へ
当サイト運営の「ホンネ不動産」なら、大家さんからの手数料を開示しているため、利益に左右されない”中立的な物件紹介”が受けられます。
不動産の不透明さをなくし、中立に、本音で提案する事を大事にしてる不動産会社なので、物件のメリットだけでなく、デメリットや「選ばない方がいい理由」まで本音でアドバイスします。「住んでから困るポイント」も事実ベースでお伝えしますので、事前に把握したい方や部屋探しで失敗したくない方におすすめです。
仲介手数料0円から選べますが、金額よりも「納得できる選択」を大切にしたい方に向いています。